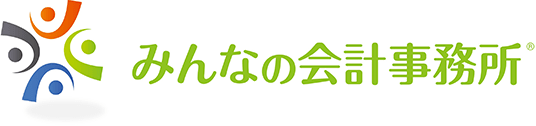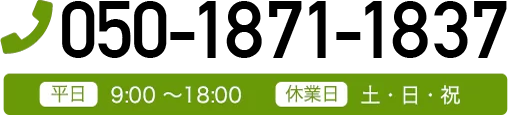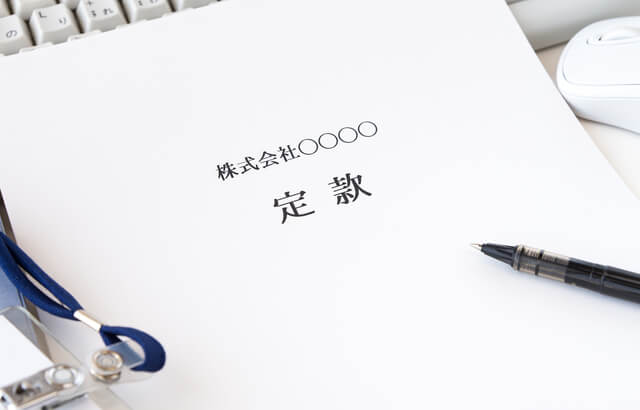会社を設立するには、資本金以外に設立手続に要する費用がかかります。これは会社の形態や設立方式によって異なります。また、司法書士や行政書士などの専門家に会社設立事務の代行を依頼する場合には別途、専門家への報酬を支払うこととなります。
今回は会社設立にあたって必要となる費用について、税理士がポイントを解説します。
会社設立に直接必要な費用
ここでは、(1)株式会社を設立する場合、(2)合同会社を設立する場合の2つのパターンの会社設立に必要な費用を示します。
(1)株式会社を設立する場合
株式会社を設立するには、まず、定款を作成し、公証人の認証を受ける必要があります。定款には収入印紙を貼り付けしなければなりません。また認証を受ける際に手数料がかかります。
さらに、法務局に設立登記の申請をする際に、登録免許税がかかります。
これらをまとめると、次のようになります。
| 定款に貼る収入印紙代 | 40,000円 |
| 公証人の定款認証手数料 | 50,000円 |
| 登記申請の際の登録免許税 |
150,000円~ |
| 合計 | 240,000円~ |
(2)合同会社を設立する場合
合同会社を設立する場合も定款を作成する必要はありますが、公証人による定款認証を受ける必要はありません。また、法務局で納める登録免許税の最低金額も株式会社よりも少なくて済みます。
これらをまとめると、次のようになります。
| 定款に貼る収入印紙代 | 40,000円 |
| 登記申請の際の登録免許税 |
60,000円~ |
| 合計 | 100,000円~ |
上記のように、株式会社の場合で約24万円、合同会社の場合で約10万円の法定費用がかかります。会社設立費用を少しでも安くするのであれば、合同会社を設立するとよいでしょう。
(関連記事)会社設立するなら「株式会社」「合同会社」どちらがいい?
その他の会社設立に必要な費用
上記の他に、会社の印鑑の作成費用(材質等によるが10,000円~)や会社設立後の手続に必要な登記簿謄本・印鑑証明の発行手数料などが必要となります。
また、司法書士、行政書士、税理士といった専門家に対して、会社設立の手続を依頼する場合は、手続き報酬がかかります。報酬は、依頼する内容や専門家によって異なります。
会社設立に必要となる費用を安くすませるためには!?
定款には「紙の定款」と「電子定款」があります。
会社設立に直接必要な費用のうち、「定款に貼る収入印紙代」は、定款を紙で作成した場合にのみ必要となります。収入印紙というのは、印紙税法で決められた文書(紙媒体)を作成したときに必要となるものだからです。
定款を電子定款で作成すれば、「定款に貼る収入印紙代」は必要なくなります。ただし、電子定款は、単にPDFデータにするだけでは足りず、電子署名を付さなければなりません。電子定款を作成するために、ソフトウェアやカードリーダーなどが必要となります。
多くの会社設立に係る専門家は電子定款に対応しています。そのため、専門家に依頼すると、定款に貼る収入印紙代が不要となります。場合によっては、専門家に依頼してもそれほど負担が変わらないケースもあります。
また、みんなの会計事務所の会社設立プラン「みんなの会社設立」では、会社設立後の税理士顧問もお任せいただける場合は、設立手数料ゼロで、会社設立をサポートしています。
(関連記事)会社設立時の電子定款とは?メリット・デメリットは?
まとめ
会社設立費用がいくらかかるかについて解説しました。会社形態を株式会社にするか合同会社にするか、定款を紙で作成するか電子定款にするか、専門家に依頼するかどうかによって費用がかかってきます。うまく専門家を使いながら、スムーズに会社設立できるとよいでしょう。
これから会社設立をされる方におすすめ「マンガでわかる!会社の税金」
ご希望の方に無料で贈呈しています。
お問い合わせページより「マンガでわかる!会社の税金希望」とご記入の上、送信してください。送付先の住所・氏名もご記入ください。
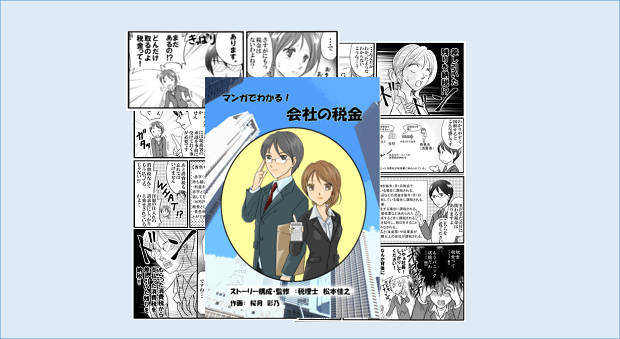
Youtube版はこちらから