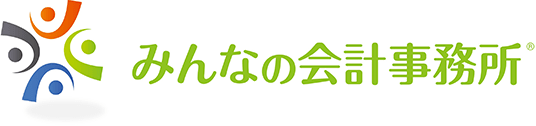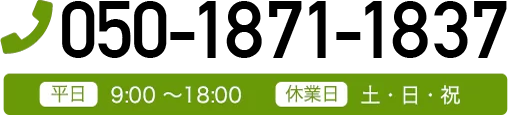これから会社設立するのであれば、会社の印鑑が必要となります。ここでは、会社設立にあたって、どのような印鑑が必要になるのか?それぞれの印鑑の役割などについて解説します。
会社設立時に必要となる印鑑の種類

電子化の流れの中で、印鑑を使う場面は以前よりは減っていますが、それでもまだまだ印鑑を使う場面は出てきます。通常、会社設立時に、次のような印鑑を作成します。
|
①代表印(実印) |
このうち、①代表印(実印)と②銀行印はほぼ必須であると言えるでしょう。銀行印と代表印を同じ印鑑とすることもできますが、別々にしておくと、代表印は代表者が管理し、銀行印は財務担当が管理するなど、使用場面と管理者を分けることができるため、リスク管理としても有用です。③角印と④ゴム印はあれば、必ず作成する必要はありませんが、あると便利なものです。
それぞれの印鑑は次のような役割を持っています。
代表印(実印)
代表印は、会社設立を行い、会社を法務局で印鑑登録する際に必要になる印鑑です。印鑑登録をすることにより印鑑証明書を発行することができるようになります。
会社設立後は取引先と契約を締結するときの契約書など重要な書類を作成する際に使います。
丸形で、円の外側に「会社名」、円の内側に「代表取締役之印」と刻印するのが一般的で、
代表印のみ、大きさに次のような制限があります。
『辺の長さが1cm超であり、3cm以内の正方形の中に収まるもの』
この大きさの制限を満たしていないと、印鑑登録することができないため注意しましょう。
なお、代表印は、丸形にするのが一般的ですが、大きさの要件を満たしていれば必ずしも丸にする必要はなく、四角の代表印を作成することもあります。
銀行印
銀行印は、会社名義の銀行口座を開設する際に必要となる印鑑です。
丸形で、円の外側に「会社名」、円の内側に「銀行之印」と刻印、代表印よりは一回り小さいサイズとするのが一般的です。
角印
請求書や見積書など会社が発行する書類に使います。必須ではありませんが、紙で請求書や見積書を発行する際に角印を押す慣行が定着しています。
ゴム印
会社名や代表者名、住所、電話番号などが入ったゴム印は、書類などを作成する際に手書きで記入する手間を省くために使います。作成が必須ではなく、あれば便利というものです。
印鑑の作成方法や作成にかかる期間
印鑑の作成は、インターネットショップ(印鑑通販サイト)で簡単に作成することができます。大きさや印鑑に使われる素材によって値段は変わりますが、代表印・銀行印・角印の3本がセットとなったもので、数千円から2万円程度のものが多いです。高品質の素材になるほど高額になりますが、小規模の会社であれば、それほど高品質のものを選ばなくてもよいでしょう。印鑑の作成には数日から一週間程度かかることが多いようです。
法人の印鑑登録の方法
印鑑登録をするには、会社設立と同時に法務局で印鑑届出を提出しておくとよいでしょう。
会社設立登記が完了すると、法務局で「印鑑カード」を発行してもらうことができます。この「印鑑カード」があれば、法人の印鑑証明書を取得することができるようになります。
まとめ
会社設立にあたって必要となる印鑑の種類について解説しました。電子化の流れの中で、印鑑を使う場面は減ってきてはいますが、それでも印鑑を使用する場面はまだあります。会社設立にあたっては、それぞれ印鑑の役割を理解しておきましょう。特に代表印や銀行印は大事なものですから紛失しないようにしっかりと保管しましょう。